国語の教科書のように最初から最後まで本を読んでいると、一冊読むのに凄まじい時間を消費してしまう。 そんなことをせず、効率的に本を読んで知識を仕入れるための方法を解説する。 忙しい人は「TL; DR」だけ読んだらいいけど、全部読んだほうが時短できると思う。
TL; DR
- 本は全部読むな
- 本は汚せ(線を引け)
- (表紙・裏表紙・帯・はじめに・おわりに・)目次を読んで、何度も出てくる言葉に赤線を引け
- 赤線が多いところを読め
- 電子書籍でも同じ
- いくらか読めば慣れてより早く読める
本編
本の分類
ここはまだ怪しいので参考程度に。
- 知識を仕入れるための本
- 入門
- 応用
- 意見
- 他にもあるかもだけど未精査
- 物語を楽しむための本
- 辞書
ここでは 1 について語る。 2 については好きなスピードで楽しく読めばいい。 3 は必要なときに使えばいい。
教科書とか単語帳とかもあるけど、1 っぽいけどあまり含めたくないなぁという気持ち。
マインド
本は一冊数千円するから、全部読まないともったいない
なんて思っていたらいつまで経っても早く読めるわけがない。 第一章で「自分には合わないな」と感じた後、第十章まで一年かけて読むのは非合理的。 その一年はあなたの時給でいくらですか?
その本から、重要な知識を最短で手に入れる。 手に入れたら金額分の価値はある。
本は大切に、綺麗な状態で読みたい
この後「線を引け」「ページを折れ」って言うんだけど、抵抗がある人がいるのは知ってる。
だけど、本の価値は綺麗さではなく「知識」。 知識を吸収できなきゃいくら綺麗でも価値はゼロ。
中古で売るくらいなら読み返してちゃんと知識を手に入れろ。
この文章、全然理解できない
それでいい。 一回で全部を理解しようなんてしなくていい。 何回でも読み直せるんだから。
原因はいくつかある。
- 自分の知識・スキルが足りてないなら、基礎知識を学んでから読み返せばいい
- 分かりづらいなら分かりやすい本を読めばいい
- 興味がないなら読まなくていい
- 疲れてるなら休め
読むの遅いから読みたくない
逆。読まないから遅いまま。
仕事や趣味と同じように、読書には技術が必要だから最初のほうは遅い。 何冊か本を読んでいるうちにコツを掴んできて読むスピードも上がる。 本全体の読み方もそうだし、個別の文章の読み方もそう。
読み飛ばしていい部分が感覚的に理解できるようになると楽になる。
読書技術
重要な知識を探す
重要な情報は、目立つところに何回も書かれていることが多い。
重要な情報がわかったら本全体が何となく理解できたも同然。 個別の文章を読むときも最終的に言いたいことがわかっているので理解しやすい。
活字のままだと見逃すので、赤線を引く。 おすすめはボールペン。 自分の興味が惹かれるところは青線、みたいに使い分けておくとベター。 電子書籍でもマーカー引けるのでやる。
この辺は学校の授業と同じ。 「ここテストに出るからな〜〜〜」って言われたところは、線を引いて何度も読み上げて問題演習する。
以下を順番に読んでいく。
表紙・帯
本において目立つところは表紙・帯。 ここに答え=その本で言いたいことが載っていることが多い。 以下は例。
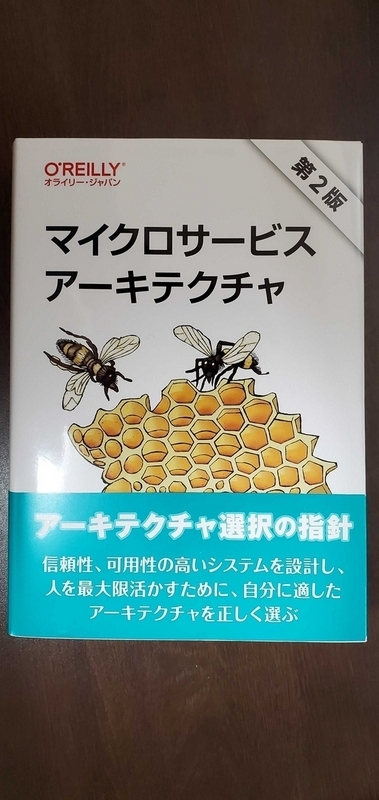
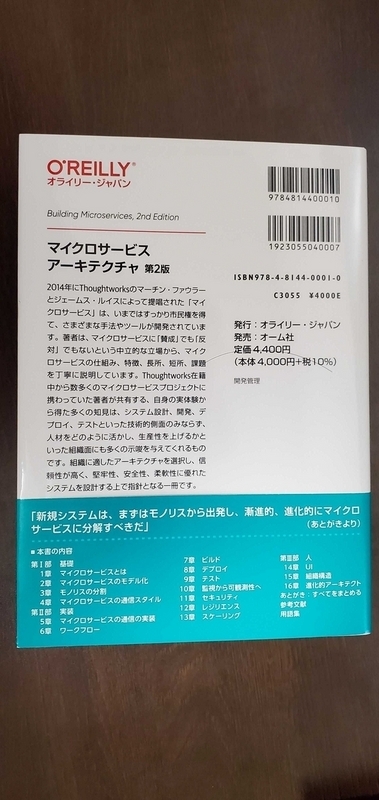
アーキテクチャ選択の指針 信頼性、可用性の高いシステムを設計し、人を最大限活かすために、自分に適したアーキテクチャを正しく選ぶ
「新規システムは、まずはモノリスから出発し、漸進的、進化的にマイクロサービスに分解すべきだ」(あとがきより)
はい、答えですね
ちなみに裏表紙にも結構いいことが書いてある
はじめに・おわりに
本に書かれている内容は筆者が言いたいことなので、筆者の気持ちが書かれている部分には答えが書かれていることが多い つまり、はじめに・おわりに(まえがき・あとがき) 「表紙・帯」セクションにある写真も、あとがきから引用したものも書かれている
目次
目次は地図だ 「どこにどんな情報が書かれているのか」がひと目見てわかる 重要な情報が密集しているところや面白そうだと思った部分に印をつけておこう それが世界で一つだけの、自分だけのお宝の地図になる
ポエム書いたんだけどここが一番重要 目次はマジで有能 もうやめなよ通読 Do you know? (ラップ)
重要なところだけ読む
お宝の地図を作った後、全世界を旅してその流れでお宝を回収する海賊なんていない 最短距離でその場所に向かうはず
本でも同じことをすればいい 目次を見て、線が多く引かれている部分を読む
何度も読みたいページや気になるページは、すぐにアクセスできるようにドッグイヤー(端っこを折る)といい 目次とか章の区切りとか折ってる 付箋は文字が書けるからいいかもしれない(けど一長一短だから自分は使ってない)
一つの本に固執しない
人は気分によって読みたい本が変わるのは当たり前 頭に入ってこないと思ったら、本を放り投げて違うことをすればいい
物語をゆっくり丁寧に読んでもいいし、アニメとかドラマを見てもいいし、ゲームをしてもいいし、運動してもいい もちろん、複数の本を同時並行で読んでもいい(おすすめだけど、逆に積んじゃうことも多い(現状 5 冊を同時並行で読んで積んでる))
アウトプットする
社内 wiki でもいいしブログでもいいし自分のメモでもいい 学んだことをアウトプットすると、頭の中でまとめる必要があるので定着しやすい 思い出すためにそれを見返せばいいので、本を読む必要がなくて楽 もう一度読んだときに理解度の差も実感できる
注意点として、文章をコピペするのは意味がない(引用くらいならいい) 文章を読んで自分の中の理解になったら、それを自分の言葉で書き直すこと 日常会話において、脳内で考えていることを言葉に出すのと同じ
その他
輪読会に役立てるには
何冊も読んで読み方を理解すれば、同じ時間でもたくさん読めるし理解度も上がる
輪読会では、大きな読み飛ばしは基本的にしないが、小さい読み飛ばしは積極的にするといい 例えば、「例えば」から始まる文章は例を挙げていることがわかるので、すでに理解できている場合は読まなくていいことが多い
「何が書かれているのか」がわかった状態で文章を読むと、比較的すんなり頭に入ってくる 各章ごとに「要約」セクションがあったら、先にそれを読んで軽く理解した後に本文を読む
参考
- 中田敦彦のYouTube大学 - 「【読書術①】たくさんの本を速く読めるテクニック」
- 前後編で全 50 分程度
- めちゃめちゃ分かりやすくまとめて動画形式になっている
- そのため、文章を読む必要がなく、文章に苦手意識のある人でも見やすい
- 「技術書」の読書術 達人が教える選び方・読み方・情報発信&共有のコツとテクニック Kindle版 - Amazon アフィリエイトリンク
- 広島修道大学 - 「要約のしかた」
- 要約のしかたがミニマルにまとまっていて読みやすいしわかりやすい
- 他にもレポート関連のコンテンツがまとまってるから参考になるかも